伸線加工品を販売する際には、ほとんどの場合で重量で管理し「円/kg」などの重量単価で販売します。
しかしながら客先の用途によっては、重量ではなく一定の長さ切って本数管理する場合があり、その際にトラブルが起きる場合があります。
実際、私のいる会社ではこの件で過去にトラブルになったそうです。
この記事では、線長での管理と重量売りで発生するトラブルについて紹介します。
伸線加工での長さと重量の関係
伸線機などは一定の「量」を伸線するために、カウンターが付いています。
このカウンターは今何m生産したのか、機械が何回転したかなどをカウントアップするもので、そのカウンター値まで巻き取ることで、一定の「量」の線を何本も取っている場合がほとんどです。
カウンター値を基準としているので、常にほぼ一定の長さの製品を生産することができていますが、実は製品の重量は大きくバラつきます。
伸線加工は伸線ダイスを使用して加工していますが、ダイスが摩耗してくると線径がだんだんと太くなっていきます。カウンター値(長さ)を基準としている方法では、常に一定のカウンター値で製品を脱着していても、重量はダイス交換直後の線径が細い状態と、ダイス摩耗が進み線径が太くなってきている状態では重量が異なります。
同じ1mでもφ1.0の線とφ1.1の線では重量が違います。
そのため、長さは管理しているが、重量は線径の出来なりで変わってくるのが伸線業界となっています。
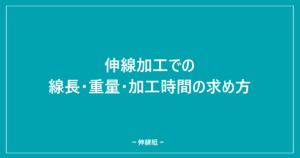
長さ管理と重量売りで発生するトラブル
伸線加工は伸線機で長さ(カウンタ)管理を行って、重量売りを行うのですが、これが客先などとトラブルを生む時があります。
客先にて一定の長さにカットして本数で生産数量を管理する場合でも、伸線した製品は○○円/kgといった量り売りがほとんどなので、φ○○mmの線を○○kgと客先からの注文を受け付け、その重量単価で販売をしています。
伸線業者はその重量の線を客先に納めるわけですが、上記で説明した通り、指定された重量ピッタリの製品を作ったとしても、線径規格範囲内だとしても、毎回同じ線径では無いため、同じ重量でも製品の長さが毎回異なります。
線径が太めの場合
線径が太めだと、同じ重量でも全長が短くなってしまうため、今まで1kgの線で10本の製品ができていたのに、8本しか製品ができないという事態が発生します。
ダイス寿命を目一杯使うために、規格上限ギリギリのものを多く作ると、客先で材料の量(重量)は同じはずなのに、材料が足らないから余分に発注しなければいけないという差異が発生して、ちょっとしたトラブルに発展することがあります。
1kgで何本できるということで原価計算・利益計算を行っている場合が多いので、客先としては追加発注分だけ通常よりも材料費が多くかかってしまうこととなりますので、線径が太い場合の方がトラブルになる可能性が高いです。
ただ、伸線業者である我々からすると、規格の範囲でものつくりをしていますので、そこは理解していただきたいところですね。
線径が細めの場合
線径が細めの場合には、同じ重量でも全長は長くなるため、今まで1kgで10本作れていたのに、12本の製品が作れたということが発生します。
こちらの場合には客先からしたら、同じ材料費で多くの製品が作れることとなり、余分な分は発注量を減らせば良いだけなので、こちらはトラブルになる可能性は低くなります。
しかしながら、このことを知って客先のことを思って細め細めで作ってしまうと、客先ではさらに少ない材料で多く作れるようになり、受注量が大きく減ってしまう恐れがあるので、その点は注意が必要です。
実際どのくらい長さは変わるのか
太いと同じ長さでも重くなるということはイメージしていただけるかと思いますが、実際問題どの程度差が出るのか計算してみます。
鉄線φ5.0の1000kgの製品で規格幅がφ4.9~5.1の場合。
・規格中央値:φ5.0mmの場合 6,490m
・規格下限値:φ4.9mmの場合 6,761m (φ5.0に比べて+271m)
・規格上限値:φ5.1mmの場合 6,240m (φ5.0に比べて-250m)
基準となるφ5.0mmから0.1mm変わるだけで、200m以上も線長が変化する計算となります。
どのような製品に使用されるのかによっても影響が異なるかと思いますが、±0.1mmの差でもここまで長さが変わってしまうということは理解しておくと良いでしょう。
もっと細く、重量も少ない製品の場合でも計算してみます。
鉄線φ0.500の10kgの製品で規格幅がφ0.495~0.505の場合
・規格中央値:φ0.500mmの場合 64,876m
・規格下限値:φ0.495mmの場合 66,180m (φ0.500に比べて+1,304m)
・規格上限値:φ0.505mmの場合 63,604m (φ0.500に比べて-1,272m)
線径が細いと±0.005mmの差なのに、1,000m以上もの差異が発生してしまいます。線径の細い製品ほど無視できない量の差になってくるのが、わかっていただけたかと思います。
線径管理と重量管理で発生する問題まとめ
今回は、客先での線長管理と伸線業の重量売りで発生する問題について紹介しました。
伸線業を行っている側から客先のことを考えると、なるべく細く作った方が良いのかと思ってしまいますが、細く作るということは、太くなる前にダイス交換を行うということになり、ダイス交換枚数も増えてしまいますので、客先からの受注量減の可能性+ダイス購入費用の増大というダブルパンチとなってしまいます。
この問題はどちらが悪いということは無く、お互いに同意して決められた規格幅で作っていると変動するものなので、お互いに理解し合う必要がある問題だと思います。
理想を言えば規格幅を決める際に、客先の使い方にもよりますが同じ重量でも長さが変動するという点について話し合いができれば、後々のトラブルはなくせるのではないかと思います。
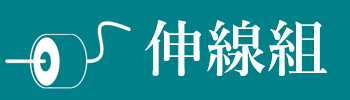
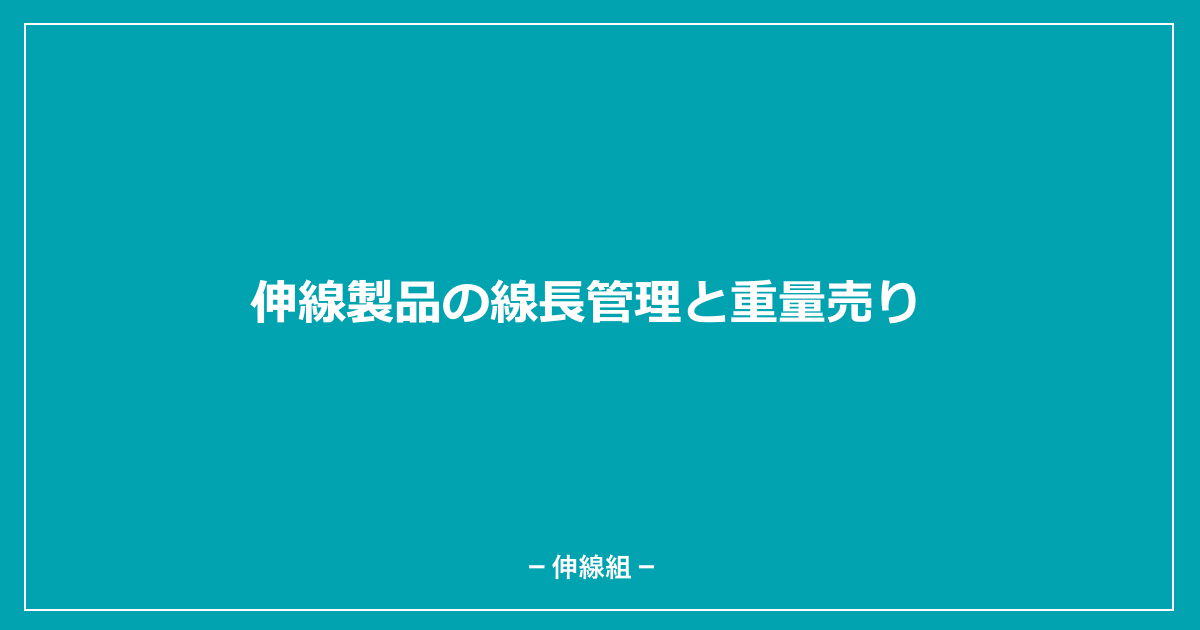
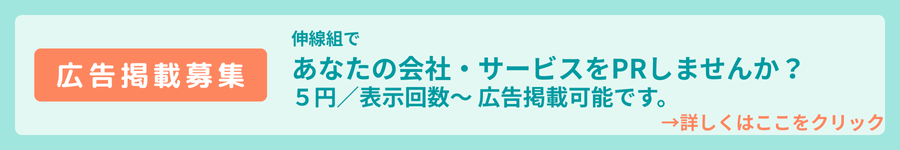
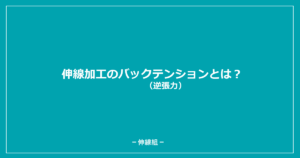
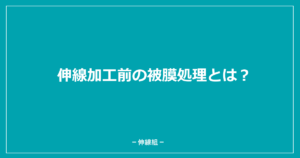
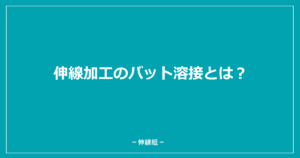
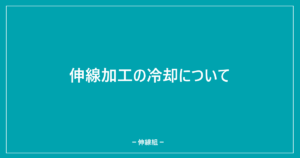
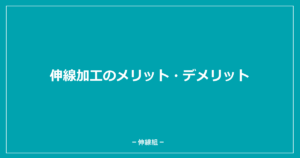
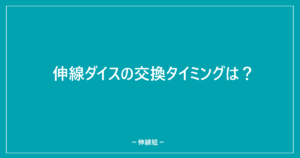
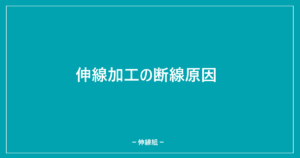
コメント