伸線加工を行う元となる線材は、製鉄会社にて製造されているのですが、どのような手順で作られているかご存じでしょうか?
鉄というものは、鉄鉱石を元にして作るものだということは広く知られていますが、石の状態からどのように鉄にして、形を作っていくのかまで知っている方はあまり多くないかもしれません。
この記事では、伸線加工を行う前のロッド材が、どのように作られているのか紹介します。
伸線加工前のロッド材とは
ロッド材とは伸線加工を行う前の、製鉄会社(日本製鉄・神戸製鋼・JFEスチールなど)から送られてきた状態の線材のことです。
製鉄会社によって線径のラインナップは異なりますが、数ミリから数十ミリまでと幅広く、カーボン値やその他の添加物によって鋼種が異なり、硬さや粘り強さの違いなどの様々な特徴を持った鉄が用意されています。
鉄の伸線加工の場合には、炭素量の少なく軟らかいローカーボン(Low-Carbon)材と呼ばれる軟鋼線と、炭素量が多く硬いハイカーボン(High-Corbon)材と呼ばれる硬鋼線の2種類に分類されています。
基本的に鉄は炭素量が多いほど硬くなります。
ロッド材にはスケールと呼ばれる、灰色の酸化膜が表面を覆っているのが特徴で、この被膜が内部の鉄線を保護しており、伸線を行う前にはスケールを除去する必要があります。
ロッド材の製造方法

伸線前のロッド材は、製鉄会社で巨大な設備を使用して、以下の工程を経て製造されています。
1.製銑(せいせん)工程
焼結鉱(しょうけつこう)(粉末の鉄鉱石を焼き固めたもの)とコークス(石炭を蒸し焼きにした炭素の塊)と石灰石(せっかいせき)を交互に高炉の上から入れます。
その内部に1000℃を超える熱風を吹き込むことで、焼結鉱とコークスと石灰石が反応し、酸化している状態の焼結鉱から、酸素が抜き取られて鉄が還元されます。
還元されながら鉄は高炉の下に溜まっていき、溜まった鉄を高炉から取り出します。
鉄を取り出す際は、高炉の下にドリルで穴を開けて取り出すそうです。
この時点で鉄は完全に液体の状態となっています。
2.製鋼(せいこう)工程
製銑工程で取り出した数百トンの鉄を「転炉(転炉)」と呼ばれる大きな入れ物に入れ、酸素を吹き込みながら混ぜる事で炭素分を取り除いたり、その他添加物を入れて成分調整を行うことで、様々な特徴を持つ鉄に仕上げていきます。
ここで炭素を多く添加すれば高炭素鋼の硬鋼線になりますし、炭素を少なく調整すれば低炭素鋼の軟鋼線となります。
ここで成分調整した鉄の検査結果がミルシートです。
3.鋳造(ちゅうぞう)工程
ここまで高炉から出てきたままの液体状態の鉄ですが、型に入れて冷やすことで形を成形します。線材の場合には「ビレット」と呼ばれる細長いバーの形に冷やし固め、一定の長さで切断をしていきます。
鉄板や鉄骨の場合には板状にしたりなど、次工程で加工しやすい形に冷やし固めます。
4.圧延(あつえん)工程
線材を作る場合には連続圧延機を使用し、四角い断面形状のビレットを複数の圧延ローラーを通すことで、徐々に丸い断面形状に成形しながら狙った線径の線材に整えていきます。
圧延時にはビレットを高温で加熱し、赤熱した状態での熱間圧延を行います。
圧延の速度は分速5000m以上の加工速度を出すことが可能であり、伸線加工では考えられない速度で加工を行い、一定の長さで切断されて冷却工程へ進みます。
実際に見たことがありますが、すごい速度で鉄が細くなっていきます。
5.冷却工程
圧延工程から出てきた線は、コイラーのような機械で線を輪っか状に加工し、網でできたベルトコンベアのようなものの上に置かれていきます。
輪っかに加工された状態でも、線は赤熱した状態なのですが、そのコンベアの下から冷却用の空気を出して冷却(ステルモア冷却)を行います。この冷却速度を変える事で、線の表面に発生する酸化膜の厚みや硬さを調整して、メカデス向きの線材や酸洗い向きの線材を作り分けています。
この冷却工程は圧延工程と繋がっており連続で行われるのですが、あえて別工程とさせてもらいました。そして冷却された線は検査されコイル状に鉄帯で束ねられて、それぞれ伸線加工業者などに納品されます。
さらに知りたい方は日本製鉄のサイトで紹介されていますので、ご覧になってみてください。
電気炉材とは
最近は脱炭素という言葉を多く聞く機会があり、身近なところでは二酸化炭素を出さないで走る電気自動車があります。
様々な業界で脱炭素を推進していますが、製鉄業界も例外ではなく脱炭素の動きがありますが、高炉で作る鉄は鉄鉱石から鉄を還元する過程で、どうしても多くの二酸化炭素を排出します。
製鉄会社の方は高炉はある意味、二酸化炭素製造機だと言っていました。
そこで電気で鉄を溶かして製鉄を行った材料の電気炉材は、環境に良いのでは?ということで注目されています。
電気炉で作った鉄は鉄鉱石からではなく、集めた鉄スクラップを溶かして再利用したものになり、資源の再利用という面からもエコっぽく注目されてきているようです。
また、元の材料が鉄スクラップなので、電気炉材は鉄鉱石から作る高炉材よりも、安く購入することができます。
電気炉のメリット
最大の特徴としては電気炉材の材料はスクラップ(鉄くず)なので、鉄鉱石から鉄を作る高炉材よりも価格が安いです。
電気の力で溶かすので、二酸化炭素(CO2)の排出量も少なく、また材料がリサイクル材となるので脱炭素(カーボンニュートラルなど)の面では、高炉材よりも圧倒的に有利な材料となっています。
また、電気の力が直接熱になるので、効率が良く省エネルギーで鉄を再利用することができます。
電気炉のデメリット
金属の不純物(銅やスズ)が混入してしまい、高品質な鉄の製造には限界があります。
電気炉材は二酸化炭素も排出せず、鉄スクラップの再利用を行うためエコの観点からいうと良いのでしょうが、元の材料がスクラップ(鉄くず)なので、様々な不純物が入っている可能性が高炉で作った鉄よりも大きくあります。
スクラップ材も素材で分別はしていますが、完全ではありません。
塗装などの有機物は燃えて無くなってしまいますが、銅やスズなど金属類は残ってしまい、これらの金属類を完全に取り除くのは現在の技術ではまだ難しいようです。
特に不純物として混入した銅は、鉄の靱性(粘り強さ)をなくしてしまうため、スクラップの中には混入しないように注意されています。
伸線加工前のロッド材ができるまで まとめ
今回は伸線加工を行う前のロッド材ができるまでを、簡単ですが紹介しました。
溶けた状態の製鋼工程までは、伸線を行う線材も鉄骨や鉄板などと基本的には同じで、溶けた鉄をどのような形に加工するのかで用途が分岐してきます。
どのように鉄が作られているのかということは、直接的に伸線加工で役立つ知識ではありませんが、自分たちが使っている材料がどのような過程を経て手元に届いているのかというのは、知っておいて損はないのかなと思います。
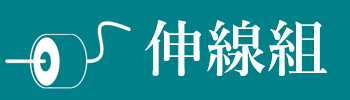
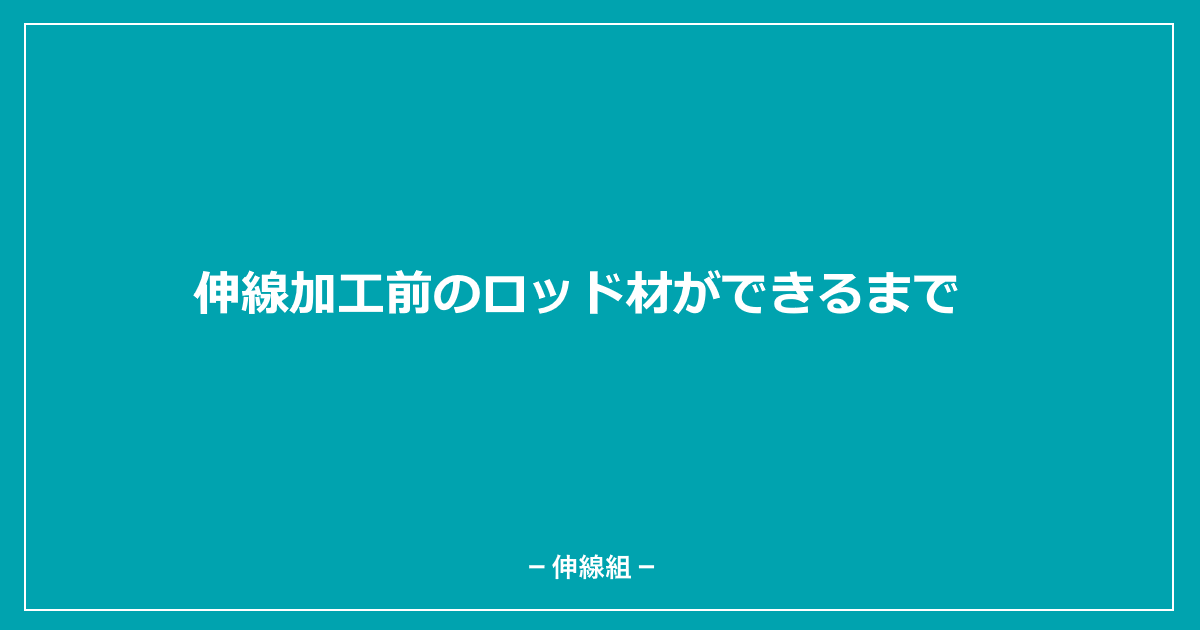
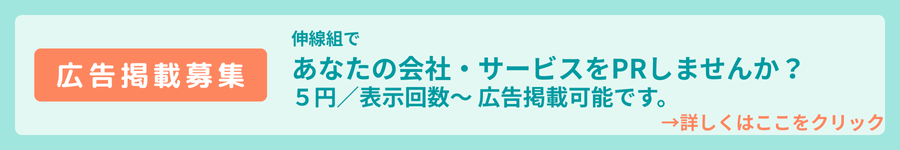
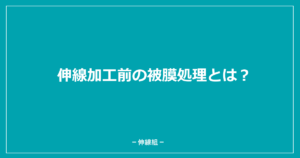
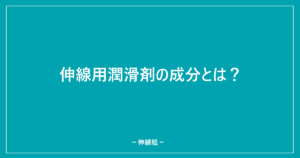
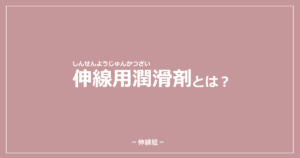
コメント